ゲーム好きなら誰でも一度は憧れるのはゲームショップのアルバイトではないでしょうか?
私は90年代半ばに約1年半のゲームショップでのアルバイト体験があるので、その時期の経験した事と衰退した理由をまとめました。
面接
90年代半ばまで中古ソフトを扱うゲームショップは結構ありましたが、あまりバイトの募集はしていなかった印象があります。
それだけ人気のある職種だったのかも知れません。
ある日、求人雑誌に某大手チェーンのゲームショップバイト募集が掲載されていたので以前からやってみたかった私は応募しました。
履歴書の志望動機には「ゲームが好きなので」って書きました。
面接にはショップのオーナーが立ち合いました。
かんたんな面接が一通り終わると「じゃ明日から来れる?」と言われあっさりと採用となりました。
働いていたショップについて
私がバイトに採用されたのは某大手チェーンゲームショップのフランチャイズ店で最盛期には日本全国で100店舗以上あったそうです。
オーナーはその店を含めて3店舗を手掛けていると話していました。
立地は地方都市の駅から5分ほど歩いた雑居ビルの2階とあまり条件は良くありませんでした。
店内は決して広くはありませんが、プレストとサターンのデモプレイ用実機とゲーセンに置いてあるアーケード機が2台置いてありました。
スタッフの構成
オーナー以外に店長と私を含めてバイトが2名だけという小さなゲームショップでした。
店長はガチのゲームオタクでレアなゲームが入荷すると店頭に出さずに自分でキープして30%の従業員割引きでよく購入していました。
商品の構成
当時はプレイステーションが発売したばかりという時期ですが、まだ中古販売が許可されていませんでした。
ネットを使って個人間でいくらでも中古ソフトを取引できる現在では笑い話ですが、まだインターネットが普及する以前、メーカーは本気で中古ゲームソフトを撲滅しようとしていたと言うそんな時代でした。
取り扱いできる最新の中古ハードはセガサターンなのですが、あまり人気がなく弱いのでまだスーパーファミコンがまだ主流でした。
すでにファミコンはレトロゲームになっていて店舗の一角にだけ置いてあるって感じでした。
業務内容
まあ色々バイトはやりましたが、トップレベルで楽なバイトでしたね。
同じ接客業のコンビニは、駅前だと絶えずお客が来て定時に届く商品の搬入とかあって大変なんですが、ゲームショップだったら買い取った商品を並べるだけなのでそれもないし、接客のマニュアルとはも特になかったし、ゆるかったです。
お客さんが来ない雨の日なんかは店長と当時流行していたバーチャファイター2で対戦して遊んでいました。
掃除
仕事の最初と最後の10分くらい行っていました。基本、ほうきで掃くだけです。
客からの買取
ときどきソフトを売りに来るお客さんから買取をします。
買取金額は本部から送られてくる価格表に従って決めるのでかんたんでした。
たまに未成年が売りに来るので保護者の同意書があるかも確認します。
買い取った商品は、クリーニングをして店頭に並べます。
その時の手順はこちらで紹介しています。
販売価格もマニュアルに従いますが、ファミコンに関しては結構好きな価格を付けても良かったので楽しかったです。
たまに買取不可の状態が悪い商品をお客さんが置いていく事があるので、店長からもらってました。
レジ打ち
お客さんがが商品をレジに持ってきたら普通の接客業によくあるレジ打ちをします。
こちらも商品ごとにバーコードで管理していたのでかんたんでした。
他店の偵察
店長に頼まれて近くのライバル店に価格の偵察にいく事もありました。
例えば人気タイトルのドラクエやファイナルファンタジーの新作が発売されたばかりの時期に中古価格を他店でチェックして価格を高くしたり安くしたりと調整していました。
値札・POP作り
価格を変更した場合の値札の張替えや目玉商品のPOPやイラストを描いたりする事もありました。
時給
時給は時代とか地域差があるのであえて書きませんが、最低賃金ギリギリでした。
これは現在でも一緒でゲームショップの時給はメッチャ安いと思ったほうが良いです。
もしやりたいのなら好きなゲームに囲まれて比較的楽な仕事だからと割り切りが必要でしょう。
辞めた理由
ある日の朝、出勤するとオーナーと店長が揃って「話がある」と言われました。
バックヤードで「実は来月で閉店する事になった」と告げられました。
他の系列店で欠員が出そうだからそっちへ行くか?と言われたのですが、何となく他の店もこれからヤバそうな気がしたので別の仕事を探す事にしました。
仕事は楽だったけど、売り上げが本当にヤバかったので閉店するのも納得でした。
こうして私のゲームショップのバイトは約1年半ほどで終わりました。
ゲームショップが衰退した理由

SONYの中古品対策
まずゲームソフト販売は新品の場合、販売ショップ側はほとんど利益が出ません。
だから私がバイトしていた店でも予約注文分しかほとんど仕入れていませんでした。
SONYのプレステは任天堂と違って半導体の需要に影響されるロムカセットではなくプレスすれば安価で供給できるCDソフトであり、問屋を通さない直販方式をとっていたので定価自体もスーファミが1万円前後だったのに対して6千円前後と安く設定できました。
これまでのゲームソフトの定価が高い+在庫切れが多い=客が中古ゲームショップで買うという方式が成り立たなくなってきました。
ゲームショップにとって圧倒的に利益が出るのは中古販売のほうなのです。
しかし、中古販売で利益を持っていかれたくないSONYは、プレイステーションを発売してから中古ソフトの売買を禁止しました。
最初は従っていた中古ゲームショップですが、耐えられなくなったショップ側と裁判になり決着が付いたのは6年後の2000年代に入ってからでした。
その裁判で争っている間に多くのゲームショップが閉店していきました。
さらにスーパーファミコンの時代はソフトの定価も1万円前後と高く利幅が取れたのですが、プレイステーションの時代になると定価が5~6,000円程度になり、利幅が取りにくくなりました。
裁判でプレステの中古販売が認められたあともSONYが過去の名作を安価なベスト版で発売したのも地味に効いていたはずです。
大手総合リユースチェーンの台頭
90年代半ば頃からブックオフ、ツタヤ、ゲオなどの大手の総合リユースチェーン店が台頭してきました。
これらのショップはゲーム以外にも本やCD、DVDなども取り扱っており、店舗も大きいのでゲーム専業で小型店舗中心のゲームショップは苦戦を強いられるようになりました。
最近ではこれらの大手ですら、ゲーム売り場を縮小したり店舗の閉鎖を余儀なくしています。
インターネットの普及
90年代までは基本、中古ゲーム売買をしようと思ったらゲームショップに持ち込む以外に選択肢がありませんでしたが、2000年代に入ってからヤフオク、Amazonなどの選択肢が増えました。
さらに2010年代にはメルカリに代表されるフリマアプリが生まれ、個人売買が活発化してソフトのダウンロード販売も増えてきました。
2020年度の任天堂のゲーム販売に占めるダウンロード販売(デジタル売上高)はついに過半数に達しました。

こうしてインターネットの普及により、ゲームショップはますます不利な状況になっていきます。
まとめ
私がゲームショップでアルバイトをしていた時期はかなり昔なので、現代だったらもっときっちりしてるでしょうけど、基本はこんなもんかなと思います。
ゲームショップのバイト経験からゲームショップ業界が衰退した原因を大まかにまとめます。
- ゲームソフトがロムからディスクになり供給が安定して安価になった事で利幅が取れなくなった。
- メーカーから中古販売禁止の圧力と長期間の裁判による業過の疲弊。
- 大手総合リユースチェーンが台頭して太刀打ちできなくなった。
- インターネットが普及した事でショップに行く必要が薄れた。
そして90年代までのゲームをショップで購入して飽きたらまたショップに売るというビジネスモデルが通用しなくなり循環サイクルが崩れたのが大きな要因でしょう。
さらにテレビゲームの主な客層である低年齢層は少子化により年々少なくなり、スマホの無料ゲームとダウンロード販売が主流となっていく中でますますパッケージ販売のゲームが売れにくくなっていきました。
バイトしていたチェーン店の本部も今では破産してしまいましたが、ゲームショップの経験が今こうしてゲーム関係のブログを書いている上てちょっと役に立っているのでやっぱり経験して良かったです。
今でもたまにあのバイトしていた時のオーナーと店長何してるのかな?とか思ったりします。
実店舗のゲームショップがほとんどなくなった現在ではネットでゲーム買取をしているサイトが増えています。

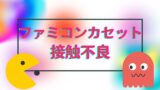



コメント